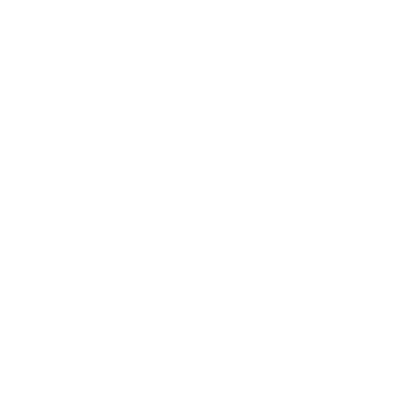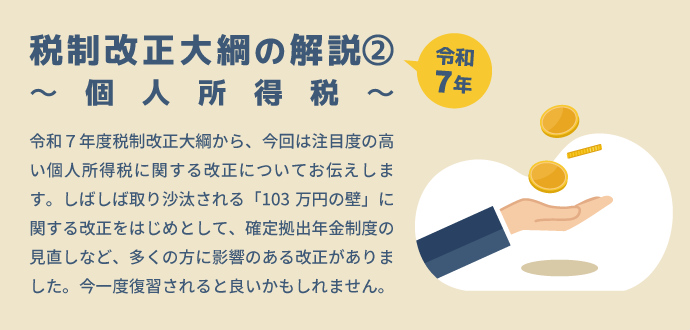
1.はじめに
前回は、令和7年度の税制改正大綱から法人税および資産課税の改正のうち、影響が大きいと思われるものついて解説しました。
今回は、最も注目度の高い個人所得税に関する改正について解説をしたいと思います。
2.所得税基礎控除等の見直し
いわゆる「103万円の壁」に関する改正です。物価上昇に伴う税負担の調整の観点から以下の2点が改正となりました。
1)基礎控除の引き上げ
合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額が、現行の48万円から58万円へと10万円引き上げられます。
2)給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得控除について、現行の55万円の最低保障額が65万円へと10万円引き上げられます。
この結果、48万円+55万円=103万円の壁が58万円+65万円=123万円まで引き上げられます。
上記の改正は令和7年度の所得税から適用され、住民税は令和8年度分から適用となります。
3.特定親族特別控除(仮称)の新設
配偶者の「103万円の壁」と同様に、大学生のような子に関しても「103万円の壁」が存在していました。この壁により大学生のアルバイト就労の妨げになっているともいわれています。これに対し、人手不足解消を目的とした優遇措置として、前項の基礎控除に足並みをそろえる形で新たに特定親族特別控除が創設されます。
対象となるのは、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者等、控除対象扶養親族を除く)を有した居住者で、その親族の合計所得金額が123万円以下である場合、特定親族特別控除として、その居住者の総所得金額から以下の金額を控除することが可能となります。
| 特定親族特別控除 | |
|---|---|
| 親族等の合計所得金額 | 控除額 |
| 58万円超 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
4.確定拠出年金制度の見直し
企業年金の有無による限度額に差異を生じさせないため、以下の改正が行われ私的年金等に関する課税の公正が図られます。
【企業型確定拠出年金】(DC)
• 確定給付企業年金制度の加入者
月額6.2万円(現行:月額5.5万円)から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額
• 確定給付企業年金制度に加入していない者
月額6.2万円(現行:月額5.5万円)
【個人型確定拠出年金】(iDeCo)
• 第一号被保険者
月額7.5万円(現行:月額6.8万円)
• 企業年金加入者
月額6.2万円(現行:月額2万円)から確定給付企業年金及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額
• 企業年金に未加入の者(第一号被保険者及び第三号被保険者を除く)
月額6.2万円(現行:月額2.3万円)
【国民年金基金】
月額7.5万円(現行:月額6.8万円)
5.子育て世代に対する生命保険料控除の拡充
新生命保険料に係る一般枠の生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族を有する場合、適用限度額が現行の4万円から2万円追加され6万円となります。ただし、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の合計適用限度額は12万円で変更がありません。
6.子育て世代に対する住宅ローン控除の拡充
特例対象個人(*)が認定住宅等の新築または取得等を行い、令和7年中に居住の用に供した場合、住宅借入金等の借入限度額が上乗せされます。
| 特例対象個人 | 左記以外 | |
|---|---|---|
| 認定住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
| 一般 | 2,000万円 | |
*特例対象個人とは以下のいずれかの要件を満たす者をいいます。
• 年齢40歳未満で配偶者を有する者
• 年齢40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
• 年齢19歳未満の扶養親族を有する者
7.おわりに
今回は令和7年税制改正の第2回目として、個人所得税のポイントを解説しました。所得税について「103万円の壁」をはじめとして、多くの方に影響のある改正がありました。年末調整の際にも今一度復習されると良いかもしれません。